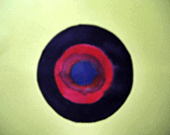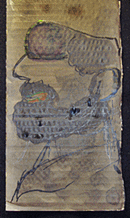存在の耐えられない重さ6 :Superheavy (デイヴ・スチュワート 中編)
2012.05.04
デイヴ・スチュワートは、1960年代の末のロンドンを中心にしたロックの大変革期…俗にスウィンギング・ロンドンと呼ばれた時代の最後の生き証人、といった風情を音楽の中に漂わせていて、それは、スーパーヘヴィの核になってやろうと、同年代のダリル・ホールらのプロデュースをやろうと、親子程も歳の違うジョス・ストーンやケイティ・ペリー達のプロデュースをやろうと、常に変わらない雰囲気のものだ。
デイヴとほぼ同世代の僕には、彼の作品を聴く時、あっ、あのアーティストのあの曲を好きなんだなとか、あの古いR&Bの曲のホーン・セクションの音を作りたくてシンセサイザーをあれこれ試したんだな、といった想像をかりたてられる所が多くて、それだけでも楽しい。