少年の耳2 :鈴懸の径
2011.11.01
デイヴ・ブルーベック・カルテットの「Take Five」を、ラジオで聴いたのとほぼ同時期の1958年頃、鈴木章治&リズムエースの「鈴懸の径」にやはり魅せられた思い出がある。
やはり、深夜のAMラジオのジャズ番組で聴き、原曲が日本の歌謡曲であり、日本のスウィング・ディキシーの草分けであるクラリネット奏者、鈴木章治が、元々3拍子のワルツの曲だったものを、4拍子のスウィング・ビートにジャズ・アレンジし、好んでライヴで演奏していたら、しだいにジャズ・ファンの心を把んできた、とその番組のDJが話していたと思う。
へぇーっ、歌謡曲も、解釈によってはジャズになるんだ、というのがその時の最初の感想で、灰田勝彦が戦時中に(1942年)録音した原曲を一緒に流されても、同じ曲だとはすぐに受け取れなかったし、3拍子が4拍子に変化するジャズ編曲の妙もすぐには解らなかった。
鈴木章治と彼のコンボが最初にレコーディングしたのは'54年の事だという。
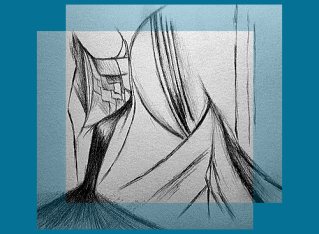
僕がラジオで聴いたヴァージョンは、鈴木が師と拝ぐベニー・グッドマンのオーケストラで主席アルト・サックス奏者を務めていたピーナッツ・ハッコーが、'57年初頭に来日した時に、この曲を聴いて気に入り、クラリネットに持ち換えてリズムエースに参加、2本のクラリネットで演奏し直した“57年版”と呼ばれているもの。
2本のクラリネットから生まれるハーモニーや音色のちょっとした違い、リズムのズレ等はとても美しく、十代に達したばかりの小僧だった僕には、とても“日本の楽曲”とは思えなかった。
ハッコーが、独自に、「Platanus Road(プラタナス・ロード)」という英語タイトルで録音し、欧米ツアーで必ず演奏したものだから、海外でも有名なヒット曲になり、逆輸入の形で日本でも名声を高める曲になったのである。
