存在の耐えられない重さ4 :Superheavy (A.R.ラフマーン) [2/3]
|
「あんなのほとんど同じ音楽じゃないか…」と吐いてすてるワールド・ミュージックの専門家や愛好家も多かったが、僕は、70年代のディスコ・サウンド氾濫の時にも同様の事を言う人が多く、その後、数多くのクリエイターがその世界から生まれたので、逆に、ひょっとしたら、とんでもない鬼才とは言えないまでも、異才は登場するのではないか、という予感がして、ラフマーンが手懸けたサウンドトラック盤を、少しづつ、注意深く聴くようになった。 ちょうど、ロンドンのヒップホップ/R&B・シーンに、インド系ラッパーやトラックメーカー、タルヴィン・シンのようなDJ/プロデューサーがあらわれ、また、コーナーショップのようにシタールを始めとしたインド楽器を効果的に導入するロック・グループも話題になってきた時期と一致していたからである。 |
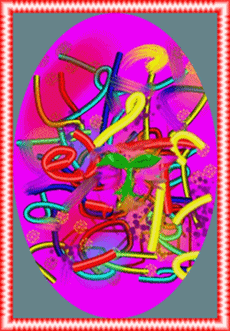
|
|

|
だが、ラフマーンの作る音楽は、そうしたロンドンのエキゾチシズムや、ビートルズやローリング・ストーンズやドノヴァンが60年代末にインド音階に傾頭したものへのノスタルジーの波に乗るレベルのものではなく、もっとスケールの大きなものだった。 サウンドトラック作品の随所に、タミル人としてのアイデンティティを活かした要素は動員されているが、それ以上に、クラシック音楽全般、過去の映画音楽、果ては、プログレッシヴなロックやソウル・ミュージック等への知識やその応用が満載されていて、これは本当に才能とスタミナに恵まれたおもしろい音楽家だという事が、じわじわと解ってきたのである。 |
|