少年の耳3 :Jazz A Saintgerman(ジャズ・ア・サンジェルマン)[3/3]
第2次世界大戦の終結直後、サンジェルマン・デ・プレ地区には、ジャズやアフリカン・ミュージックのミュージシャンだけではなく、画家、詩人、映像作家、ダンサー、俳優等、凡そフランスの文化のその後を代表する事になる文化人の卵が昼夜集まり、ジャズに乗って踊っていた、という文化史エピソードはあまりにも有名で、サルトルやカミュの実存主義文学もヌーベルヴァーグ映画も、その中から芽を出した、といった説は、一説を超えて伝説となっている。

確かに、その1950年代のサンジェルマン・デ・プレの街の、ジャズを核とした“熱”が無かったら、マイルス・デイビスが映画『死刑台のエレベーター』の音楽を、フィルム・ラッシュを観ながら即興で吹きこんで、知名度と人気を高める事も無かっただろうし、後年、ニュー・ウエイヴ世代のロックやポップのアーティストが、サンジェルマンへの敬意をこめたオマージュのようなアルバムの為に集結する事も無かっただろう。
『ジャズ・ア・サンジェルマン』のライナーノーツを執筆している時、1950年代末から60年代にかけて、よく通った故郷のふたつの映画館の椅子やスクリーンの感触を思い出した。
邦画2本に洋画1本の3本立(だて)なんてメニューは当たり前の時代…その中に付録のように組まれているジャン・ギャバン主演の映画なんかを一番熱心に観ていたのだが…
フランスが、アフリカやカリブ海にいっぱい植民地を持っていた国だという事すら知らない少年にとっては、フランス映画の中に、どうしてジャズや黒人民族音楽がよく流れ、アルジェリアの町の風景等がよく登場するのか、不思議でならなかった。
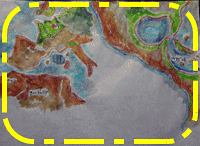
そのあたりを少し理解したのは、'67年に沢たまきや緑川アコの歌で聴いた「カスバの女」の歌詞だったのが正直なところ。
この不思議な歌謡曲については、また別の機会に書こうと思うが、アルバム『ジャズ・ア・サンジェルマン』にも、よくは知らないパリの伝説の一画に漂っていたであろう熱や空気への思いはこもっている。
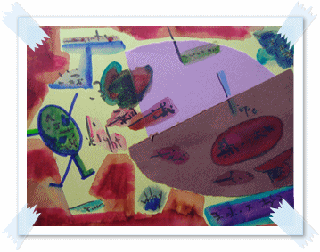
僕は、その蜃気楼のような空気を感じながら、楽曲やアーティストの解説を素直に書いた。
担当ディレクターに初めてうけたのはそのせいか…彼には、「カスバの女」の事は一言も話していない。