青春の子守歌 (サンタナ : Santana) [2/3]
|
サンタナといえば、ビートルズが解散するかしないかと噂されていた60年代の末に、サンフランシスコのライヴハウス“フィルモア・ウエスト”を根城にぐいぐい乗してきたロック・バンド。 ポスト・ビートルズの、ニュー・ロック/アート・ロックの時代に入って、最初に知名度を高めた人気ロックバンドだ。 ちょうどその時代を十代の終わりの年代ですごし、大学生活をおくり、ロック喫茶に入り浸たり、ライヴDJを売りにしている新宿のロック喫茶で初めてアメリカン・ロックを担当するアルバイトDJを経験した時、まだ発売されたばかりのデビュー・アルバムや、その後、世界的な破格のセールスを記録するセカンド・アルバム『天の守護神/Abraxas その辺の体験を、NHK-FMの特番で話した事があるが、聴いてくれた同級生や同世代の人の半分位は「がっかりした」とか「あんな脳天気のバンドを取り上げて…」とか、割とネガティヴで批判的な感想をくれた。 |
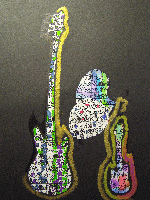
|
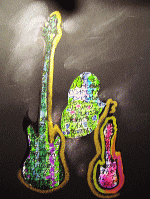
|
サンタナは、リーダーのカルロス・サンタナの官能的なギターと、60年代から70年代にかけてのロック界ではとても珍しいラテン要素全般を取り入れた個性あふれる躍動感が売りの特異なバンドである。 「ブラック・マジック・ウーマン」を始めラジオやジューク・ボックスの定連(じょうれん)となるポップ・ヒットも数多く、メンバーはよく変わるが長命で、カルロス・サンタナはずっと現役第一線で活動し、いまだ健在だ。 ニュー・ロックやアート・ロックの洗礼を受けた世代には、その独得の音楽スタイルとポピュラリティの高さ、そして、時には「哀愁のヨーロッパ」や「ムーンフラワー」のように、日本の歌謡曲かと見まがうようなメロディアスなヒット曲を憶面もなく作り出してしまうあたりが、逆に、あざとく、うさん臭く、知性に欠けるロックと写るのかもしれない。 批判の声の中には、レッド・ツェッペリンを取り上げないであんな軽いバンドをわざわざ取り上げるなんて、といった意見が多く、その時、サンタナのパブリック・イメージ、ひいては、南米やアフリカの音楽に対する実は歪んだ視線に、遅まきながら気づかされたものだ。 |